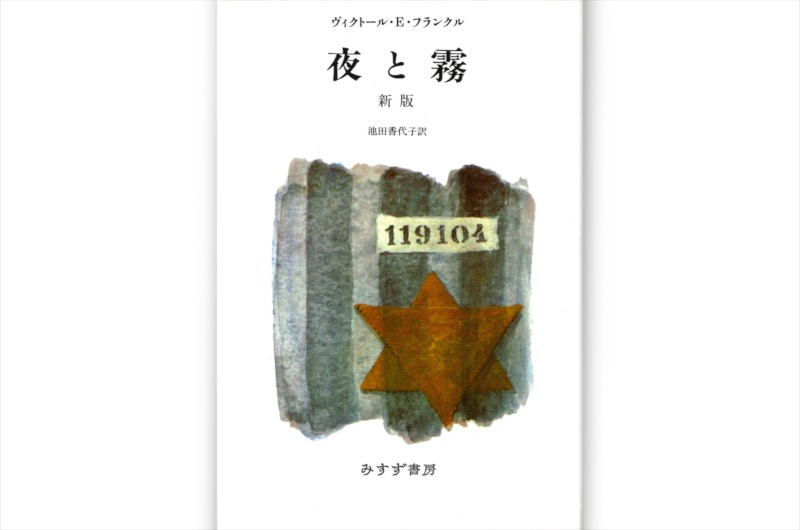アウシュヴィッツでもこれと同じような、世界をしらっと外からながめ、人びとから距離をおく、冷淡と言ってもいい好奇心が支配的だった。さまざまな場面で、魂をひっこめ、なんとか無事やりすごそうとする傍観と受身の気分が支配していたのだ。わたしたちは好奇心の塊だった。
人間はなにごとにも慣れる存在だ、と定義したドストエフスキーがいかに正しかったかを思わずにはいられない。
人間はなにごとにも慣れることができるというが、それはほんとうか、ほんとうならそれはどこまで可能か、と訊かれたら、わたしは、ほんとうだ、どこまでも可能だ、と答えるだろう。
だが、どのように、とは問わないでほしい……。
どんな環境にも慣れてしまう。その慣れ方は人それぞれ。
環境に染まる人もいれば、内面的に深まる人など。
苦しむ人間、病人、死の人間、死者。これらはすべて、数週間を収容所で生きた者には見慣れた光景になってしまい、心が麻痺してしまったのだ。
環境には慣れる。
感情の消滅や鈍磨、内面の冷淡さと無関心。これら、被収容者の心理的反応の第二段階の徴候は、ほどなく毎日毎時殴られることにたいしても、なにも感じなくさせた。
自集団の一部であり、個としての自覚が消滅する。
被収容者仲間のうち、精神分析に関心のある同業者たちのあいだでは、収容所における人間の「退行」、つまり精神生活が幼児並みになってしまうことがよく話題になっていた。この願望や野心の幼児性は、被収容者の典型的な夢にはっきりとあらわれた。
環境によって人間は退行することも大いにありえる。退行しないためには自分が置かれた状況下で何を考えどう動くか、ということは非常に重要である。
そのとき自分の裸の体を見て考えることは、みな同じだった。これがわたしの体か?これはもう死体じゃないか。わたしとはいったいなんだ。人の肉でしかない大群衆の、けちなひと切れだ。鉄条網のなかでいくつかの掘っ立て小屋に押しこまれている群集、毎日きちんきちんと決まった割合で命を失い、腐っていく群衆のけちなひと切れだ。
収容所の話ではあるが、集団に属すると否が応でも考えさせられる。収容所であるから、それがより鮮明になっている。
被収容者はほとんどまったくと言っていいほど、性的な夢をみなかった。他方、精神分析で言う「手の届かないものへのあがき」、つまり全身全霊をこめた愛への憧れその他の情動は、いやというほど夢に出てきた。
夢は感情の現れなのか。昔はよく見ていた夢を最近では余り見ることがなくなった。
感情が死んでいるのだろうか・・・?
被収容者は、生きしのぐこと以外をとてつもない贅沢とするしかなかった。あらゆる精神的な問題は影をひそめ、あらゆる高次の関心は引っこんだ。文化の冬眠が収容所を支配した。
抑圧された環境では、「生きる」ことしか考えられなくなる。「あり方」を考えるなどという余裕もなくなる。
愛は人が人として到達できる究極にして最高のものだ、という真実。人は、この世にもはやなにも残されていなくても、心の奥底で愛する人の面影に思いをこらせば、ほんのいっときにせよ至福の境地になれるということを、わたしは理解したのだ。
これやってみたけどガチ。愛の力はすごいなと思った。
たとえば、おいしい食べ物を想像しても至福感はなかったが、愛する人の面影を目をつぶって想うと、ほんわかした至福の心地になった。
もしもあのとき、妻はとっくに死んでいると知っていたとしても、かまわず心のなかでひたすら愛する妻を見つめていただろう。心のなかで会話することに、同じように熱心だったろうし、それにより同じように満たされたことだろう。あの瞬間、わたしは真実を知ったのだ。
この世にいてもいなくても愛は変わらない。なくならない。
愛はいつも心の中にある。
被収容者の内面が深まると、たまに芸術や自然に接することが強烈な経験となった。この経験は、世界やしんそこ恐怖すべき状況を忘れさせてあまりあるほど圧倒的だった。
逆に内面が深まらないと、自然や芸術に興味を持てないのでは?
であれば、自然や芸術に興味を持てる人は内面が深まっている人なのでは?
わたしたちは数分間、言葉もなく心を奪われていたが、だれかが言った。
「世界はどうしてこんなに美しいんだ!」
自然は最強に美しい。自然には敵わない。自然に触れ合おう。
人間の命や人格の尊厳などどこ吹く風という周囲の雰囲気、人間を意志などもたない、絶滅政策のたんなる対象と見なし、この最終目的に先立って肉体的労働力をとことん利用しつくす搾取政策を適用してくる周囲の雰囲気、こうした雰囲気のなかでは、ついにはみずからの自我までが無価値なものに思えてくるのだ。
自我の喪失。自我を持つことが許されない世界。
内面の自由と独自の価値をそなえた精神的な存在であるという自覚などは論外だ。人は自分を群集のごく一部としか受けとめず、「わたし」という存在は群れの存在のレベルにまで落ちこむ。
わたしはあくまで集団の一部であり、集団から独立した個ではない。ただ、集団に存在している人を圧倒的に自覚させられる。大組織の構造にもに似ているかもしれない。
主体性をもった人間であるという感覚の喪失は、強制収容所の人間は徹頭徹尾、監視兵の気まぐれの対象だと身をもって知るためだけでなく、自分は運命のたわむれの対象なのだと思い知ることによっても引き起こされた。
思いかけず、収容され虐げられる。自分の人生は自分でどうにもならない感覚=主体性感覚の喪失
ただただ、「運命」という大きな潮流に流される存在。
自分はただ運命に弄ばれる存在であり、みずから運命の主役を演じるのでなく、運命のなすがままになっているという圧倒的な感情、加えて収容所の人間を支配する深刻な感情消滅。こうしたことをふまえれば、人びとが進んでなにかをすることから逃げ、自分でなにかを決めることをひるんだのも理解できるだろう。
人や環境によるが選択できるのであれば現代は主体性が持て、主体性を求められる時代。
肉体的な要因は数あるが、筆頭は空腹と睡眠不足だ。周知のように、ふつうの生活でも、このふたつの要因は感情の消滅やいらいらを引き起こす。
だめ絶対。なによりも優先度が高いものたち。
人は強制収容所に人間をぶちこんですべてを奪うことができるが、たったひとつ、あたえられた環境でいかにふるまうかという、人間としての最後の自由だけは奪えない
かつてドストエフスキーはこう言った。
「わたしが恐れるのはただひとつ、わたしがわたしの苦悩に値しない人間になることだ」
『苦しいときに、腹をくくりながらも「なぜ?」と考えること』だそう。
自分が苦しい状態であるときに、しっかりと苦悩(なぜ?と考える)する。それが人間の価値や強さである。
およそ生きることそのものに意味があるとすれば、苦しむことにも意味があるはずだ。苦しむこともまた生きることの一部なら、運命も死ぬことも生きることの一部なのだろう。苦悩と、そして死があってこそ、人間という存在ははじめて完全なものになるのだ。
苦悩や死は生きることに内包されている。
ひとりの人間が避けられない運命と、それが引き起こすあらゆる苦しみを甘受する流儀には、きわめてきびしい状況でも、また人生最期の瞬間においても、生を意味深いものにする可能性が豊かに開かれている。勇敢で、プライドを保ち、無私の精神をもちつづけたか、あるいは熾烈をきわめた保身のための戦いのなかに人間性を忘れ、あの被収容者の心理を地で行く群れの一匹となりはてたか、苦渋にみちた状況ときびしい運命がもたらした、おのれの真価を発揮する機会を生かしたか、あるいは生かさなかったか。そして「苦悩に値」したか、しなかったか。
・集団心理に流されずに自分を保ち人間性を失わずにいられるか
・苦悩できるか
・苦しくても無私(私心・我利・我欲・エゴなどの「自分のため」といった感情がない状態)でいられるか
人生最後の瞬間までにこれらを行うことで、よりいっそう生が輝く。
それはなにも強制収容所にはかぎらない。人間はどこにいても運命と対峙させられ、ただもう苦しいという状況から精神的になにかをなしとげるかどうか、という決断を迫られるのだ。
どこにいてもいまこの瞬間、運命と対峙をし続けている。「苦しい」「辛い」という状況から精神的になにかを成し遂げる。ここに人間的な強さが隠されている。
収容所生活の外面的困難を内面にとっての試練とする代わりに、目下の自分のありようを真摯に受けとめず、これは非本来的ななにかなのだと高をくくり、こういうことの前では過去の生活にしがみついて心を閉ざしていたほうが得策だと考えるのだ。
このような人間に成長は望めない。被収容者として過ごす時間がもたらす苛酷さのもとで高いレベルへと飛躍することはないのだ。
どのような状況下でも人間として成長する可能性を秘めている。過酷であるか、ないか、それには本質的には関係がない。「”いま”の自分の状況」を真摯に受け止めて、内面の試練とする。そして、苦悩して内面を深める。
より高次の次元へと人間的に成長をすることができる。
なので、いまの自分の課題はなにか?内面的な試練とはなにか?考えて、自分に立ち向かう。
凡庸なわたしたちには、ビスマルクのこんな警告があてはまった。
「人生は歯医者の椅子に坐っているようなものだ。さあこれからが本番だ、と思っているうちに終わってしまう」これは、こう言い替えられるだろう。
「強制収容所ではたいていの人が、今に見ていろ、わたしの真価を発揮できるときがくる、と信じていた」
「これから、本番がまわってくる。」そう考えている人はチャンスがまわってこずに人生が終わる。
いまこのときこの瞬間が人生の本番である。
強制収容所の人間を精神的に奮い立たせるには、まず未来に目的をもたせなければならなかった。
被収容者を対象とした心理療法や精神衛生の治療の試みがしたがうべきは、ニーチェの的を射た格言だろう。「なぜ生きるかを知っている者は、どのように生きることにも耐える」
仕事、人生、家族、友人。生きる理由や目的がある人は、生きることに耐えることができる。
すべてを無くす、失うと絶望をする。
ひるがえって、生きる目的を見出せず、生きる内実を失い、生きていてもなにもならないと考え、自分が存在することの意味をなくすとともに、がんばり抜く意味も見失った人は痛ましいかぎりだった。
そのような人びとはよりどころを一切失って、あっというまに崩れていった。
逆に、生きる理由(依存先とも言いかえることができる)が多ければ多いほど、もちろん辛く苦しいことも多いが、人生は光り輝く。いきいきと躍動する。
生きるとはつまり、生きることの問いに正しく答える義務、生きることが各人に課す課題を果たす義務、時々刻々の要請を充たす義務を引き受けることにほかならない。
人間は苦しみと向きあい、この苦しみに満ちた運命とともに全宇宙にたった一度、そしてふたつとないあり方で存在しているのだという意識にまで到達しなければならない。
自分は唯一無二。苦しみも、死も自分の一部。
自分を待っている仕事や愛する人間にたいする責任を自覚した人間は、生きることから降りられない。まさに、自分が「なぜ」存在するかを知っているので、ほとんどあらゆる「どのように」にも耐えられるのだ。
自分の仕事に責任を持っているか?仕事で求められているか?愛する人間がいるか?愛されているか?
「自分がこの世に存在するのか?必要なのか?」その答えが必要である。この問いは非常に重要な意味をもつ。
まともな人間とまともではない人間と、ということを。このふたつの「種族」はどこにでもいる。どんな集団にも入りこみ、紛れこんでいる。まともな人間だけの集団も、まともではない人間だけの集団もない。したがって、どんな集団も「純血」ではない。監視者のなかにも、まともな人間はいたのだから。